電気工事施工管理技士は、電気に関する工事の施工管理に必要な資格です。電気工事施工管理技士には、1級と2級がありますが、仕事内容や試験の難易度などに違いはあるのでしょうか。今回は、電気工事施工管理技士の仕事内容、試験の概要、試験の難易度について解説します。
結論からいうと、令和6年度の1級電気工事施工管理技術検定の第一次検定における合格率は36.7%、第二次検定が49.6%となっており、やや難易度が高いといえます。国土交通大臣から指定試験機関の指定を受けている「一般財団法人建設業振興基金」が公表する情報をもとに、令和7年度の実施日程や申し込みの時期についてもまとめたので参考にしてみてください。
●施工管理の求人情報を探す
> 電気施工管理
電気工事施工管理技士ができる仕事内容とは?

1級・2級電気工事施工管理技士とは、建設業法に基づく国家資格で、電気工事の施工管理に必須の資格です。電気工事施工管理技士の資格を取得すると、以下のような電気工事の施工管理に携わることができます。
- 照明設備工事
- 変電設備工事
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 構内電気設備工事
- 非常用電源設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
施工管理とは、工程・品質・原価・安全の4大管理を行なう、建設現場になくてはならない職種です。それぞれの内容は、以下になります。
| 4大管理 | 詳細 |
|---|---|
| 工程管理 | 決められた納期を守るためのスケジュール管理 |
| 品質管理 | 求められる品質基準や安全性の管理 |
| 原価管理 | 予算内での資材発注や原価の管理 |
| 安全管理 | 事故が起こらないための安全管理 |
なお、1級と2級の仕事内容はほぼ同じであり、管理できる現場の規模に違いがあります。1級は特定建設業の専任・技術者、監理技術者と認められるため、大規模な現場で施工管理に携わることが可能です。一方、2級は一般建設業の許可に必要な専任技術者、主任技術者として認められ、おもに中小規模の現場での施工管理が行なえます。
1級は工事の規模を問わないメリットがありますが、会社が請け負う工事の規模により2級で十分というケースもあります。
【2025年度】電気工事施工管理技士試験の概要
電気工事施工管理技士試験の試験科目、受検資格を見ていきましょう。
電気工事施工管理技士の試験科目
電気施工管理技士試験は、第一次検定、第二次検定にそれぞれ合格する必要があります。電気施工管理技士試験における1級・2級の第一次検定、第二次検定の試験内容は以下をご覧ください。なお、解答形式はマークシート方式です。
|
1級電気工事施工管理技士の試験の内容 |
||||
|
区分 |
検定科目 |
検定基準 |
知識・能力別 |
解答形式 |
|
第一次検定 |
電気工学等 |
|
知識 |
四肢択一 |
|
施工管理法 |
|
知識 |
四肢択一 |
|
|
能力 |
五肢択一 |
||
|
法規 |
建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 |
知識 |
四肢択一 |
|
|
第二次検定 |
施工管理法 |
|
知識 |
五肢択一 |
|
能力 |
記述 |
||
|
2級電気工事施工管理技士の試験の内容 |
||||
|
区分 |
検定科目 |
検定基準 |
知識・ |
解答形式
|
|
第一次検定 |
電気工学等 |
電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気 通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 |
知識 |
四肢択一 |
|
電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な発電設備、変電 設備、送配電設備、構内電気設備等(以下、「電気設備」という。)に関する概略の知識を有すること。 |
||||
|
電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。 |
||||
|
施工管理法 |
電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 |
知識 |
四肢択一 |
|
|
電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 |
能力 |
五肢択一 |
||
|
法規 |
建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
知識 |
四肢択一 |
|
|
第二次検定 |
施工管理法 |
主任技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 |
知識 |
四肢択一 |
|
主任技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応 用能力を有すること。 |
能力 |
記述 |
||
電気工事施工管理技士の受検資格
1級・2級電気工事施工管理技士の受検資格は、次のとおりです。
|
1級電気工事施工管理技士の受検資格 |
||||
|
区分 |
学歴 |
実務経験年数 |
||
|
指定学科卒業 |
指定学科以外卒業 |
|||
|
イ |
大学 専門学校の高度専門士 |
卒業後3年以上 |
卒業後4年6ヵ月以上 |
|
|
短大 高等専門学校(5年制) 専門学校の専門士 |
卒業後5年以上 |
卒業後7年6ヵ月以上 |
||
|
高校 中学 専門学校の専門課程 |
卒業後10年以上 |
卒業後11年6ヵ月以上 |
||
|
|
その他(学歴は問わず) |
15年以上 |
||
|
ロ |
電気主任技術者免状の交付を受けた者(種別問わず) |
免状交付後ではなく通算で6年以上 |
||
|
ハ |
第一種電気工事士免状の交付を受けた者 |
実務経験問わず |
||
|
二 |
2級電気工事施工管理技術検定 第二次検定合格者 |
合格後5年以上 |
||
|
2級電気工事施工管理技術検定 第二次検定の合格後、実務経験が5年未満の者 |
短大 高等専門学校 (5年制) 専門学校(専門士) |
区分イ参照 |
卒業後9年以上 |
|
|
高等学校 中高一貫校 専門学校(専門課程) |
卒業後9年以上 |
卒業後10年6ヵ月以上 |
||
|
その他(学歴問わず) |
14年以上 |
|||
|
ホ※ |
2級電気工事施工管理技術検定 第二次検定合格者 |
実務経験問わず |
||
(※1級受検資格の「ホ」の区分は、第一次検定のみに適用されます。第一次検定に合格しても、その年度の第二次検定を受検することはできません。)
【第二次検定】
第二次検定を受けるには、以下のいずれかに該当する必要があります。
1. 本年度第一次検定の合格者【上記の区分イ~ニの受検資格で受検した者に限る】
2. 令和2年度学科試験のみ合格者(令和3年度限り)
3. 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門または建設部門)に合格した者で、なおかつ1級電気工事施工管理技術検定第一次検定の受検資格のうち、上記区分イ~ニのいずれかの受検資格を有する者
2級
「第一次検定のみを受ける」・「第二次検定のみを受ける」・「どちらも同日に受ける」の3パターンがあり、それぞれ受検資格が異なります。
【第一次検定のみ】
「試験実施年度で満17歳以上」を満たしていれば誰でも受検できます。(令和6年度に申請する場合、生年月日が平成18年4月1日以前)
【第二次検定のみ】
第二次検定のみを受検する場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
1. 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門または建設部門に係るもの)に合格した者
2. (令和2年度までの)2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ」受検の合格者で有効期間内の者
3. (令和3年度以降の)2級電気工事施工管理技術検定の「第一次検定」合格者
【第一次検定と第二次検定を同日受検】
第一次検定と第二次検定を同日受検する場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
|
2級電気工事施工管理技士の受検資格 |
|||
|
区分 |
学歴 |
実務経験年数 |
|
|
指定学科卒業 |
指定学科以外卒業 |
||
|
イ |
大学 専門学校の高度専門士 |
卒業後1年以上 |
卒業後1年6ヵ月以上 |
|
短大 高等専門学校(5年制) 専門学校の専門士 |
卒業後2年以上 |
卒業後3年以上 |
|
|
高校 中学 専門学校の専門課程 |
卒業後3年以上 |
卒業後4年6ヵ月以上 |
|
|
|
その他(学歴は問わず) |
8年以上 |
|
|
ロ |
電気主任技術者免状の交付者(種別問わず) |
免状交付後ではなく通算で1年以上 |
|
|
ハ |
第一種電気工事士免状の交付者 |
実務経験問わず |
|
|
二 |
第二種電気工事士免状の交付者 |
免状交付後ではなく通算で1年以上 |
|
実務経験年数を計算する際は、指定の期日を基準とします。指定の期日で受検資格を満たさない場合は、試験日の前日までの日数を受検資格に含むことも可能です。ただし、複数の現場の経験を重複して計算できないなど注意点があるので、詳しくは受検要項をよく確認してください。
電気工事施工管理技士の難易度とは?

電気工事施工管理技士の合格率を踏まえた、試験の難易度を見ていきましょう。
電気工事施工管理技士の合格率
令和5年度の電気工事施工管理技士の合格率を以下の表にまとめました。
|
令和5年度電気工事施工管理技士の合格率 |
||
|
区分 |
一次試験 |
二次試験 |
|
1級 |
40.6% |
53.0% |
|
2級 |
43.8% |
43.0% |
出典:令和5年度 1級電気工事施工管理技術検定 結果表
出典:令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 結果表
なお、令和2年度までは第一次検定・第二次検定ではなく、「学科試験」・「実地試験」の旧制度で試験が行なわれていました。
ここまで紹介した新制度で実施された、令和3年度の1級電気工事施工管理・第一次検定の合格率は「53.3%」という結果となっています。
電気工事施工管理技士試験の難易度
電気工事施工管理技士の合格率は40~50%程度であり、難易度はやや高いといえます。検定試験は1級の難易度が高く、合格率が低いことが一般的ですが、電気工事施工管理技士試験では1級と2級に大きな差がありません。
令和3年度から始まった新制度の試験では、知識を問うだけの内容から、能力や実務経験に基づいた知識・能力が問われるように変更されました。一見難易度が上がったように思えますが、令和3年度の1級第一次検定の合格率が53.3%は、前年度(旧制度)の学科試験合格率よりも高い数値です。したがって、新体制になったとはいえ、問題の難易度で大きな変化はないといえるでしょう。
また、電気工事施工管理技士試験は、似た問題がくり返し出題される傾向があります。過去問を重点的に勉強すれば、合格のチャンスは十分あるでしょう。
まとめ
電気工事施工管理技士には1級と2級がありますが、仕事内容自体に大差はなく、携われる建設工事の規模に違いがあります。電気工事施工管理技士検定の難易度は、1級と2級であまり変わりませんが、1級のほうが受検資格で求められる実務経験年数が長いのが特徴です。
令和3年度からは、第一次検定・第二次検定という新体制でスタートしていますが、合格率を見ると難易度における大きな変化は見られません。過去問と似た問題が出題される傾向があるため、新体制後も過去問を重点的に勉強しましょう。
●施工管理の求人情報を探す
> 電気施工管理
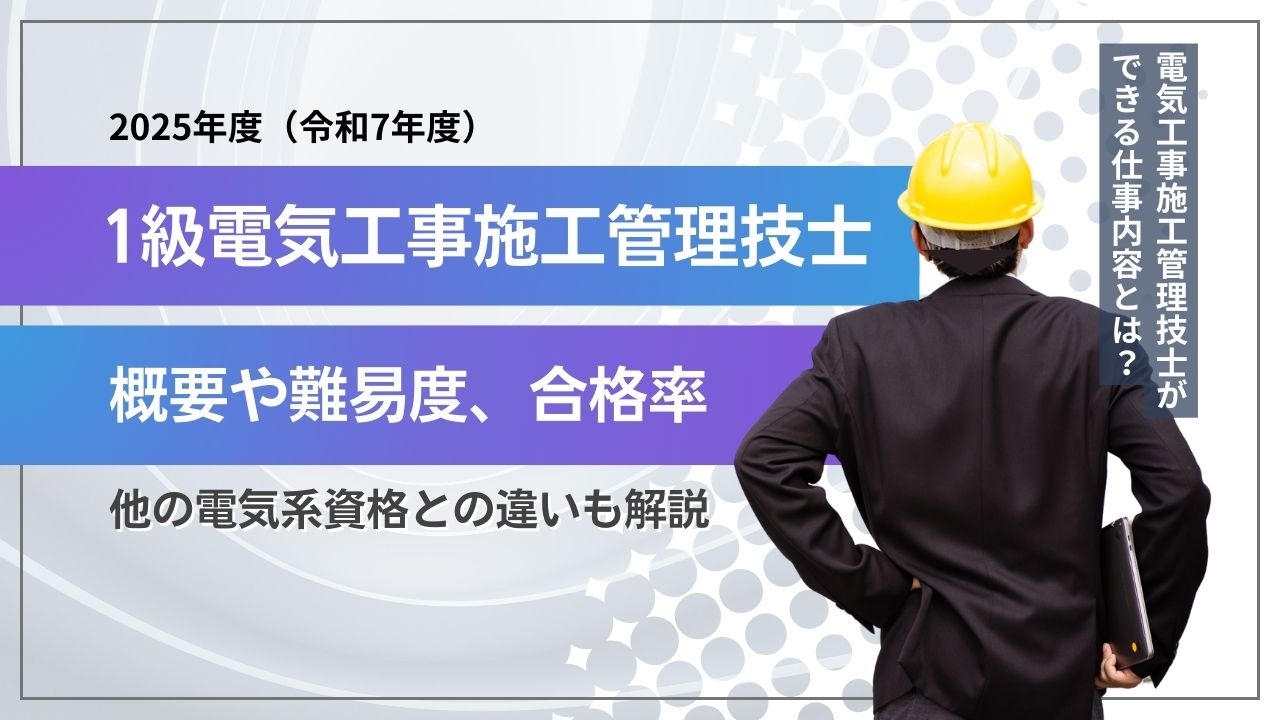



_180x98.jpg)















.jpeg)





